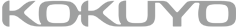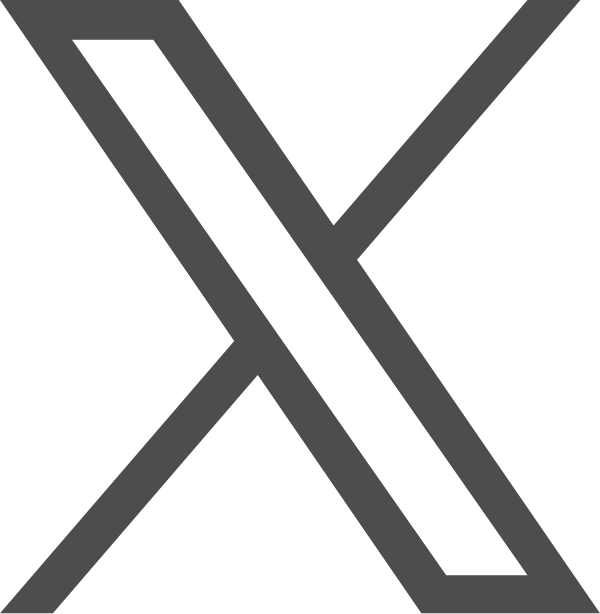KOKUYO DESIGN AWARD 2013

2013テーマ:「HAPPY×DESIGN」
これからの世界がもっと元気で、もっと幸せになるように。
豊かな感性が息づいたアイデアが、世界中から集まりました。
応募作品総数は1,217点(国内1,106点、海外111点)にのぼり、
厳正な審査の結果、グランプリ1点、優秀賞3点、特別賞4点が決定しました。
グランプリ

作者 玄多仁(ヒョン ダイン)
作者コメント
「使い切る」というエコ 使い手にもエコはあるのではないかと思い、 当たりくじが付いているペンを作りました。 「アタリ」は楽しく使い切るための工夫です。 小さい仕掛けを通じて、 作り手と使い手がつながる。 お互いのハッピーが見える。 人の幸せはエコになります。
審査員講評
見た瞬間、にこっと微笑みたくなる気持ちになるデザインで好感が持てます。最終プレゼンテーションに十分時間をかけて臨んだのがわかりました。作品だけでなく、ハプニングがあっても押し通すだけの用意をしていた点を評価します。
川島 蓉子
ひと目見てパッとすぐにわかること。それは強さです。誰もが考えつきそうで今までになかった良いアイデアを、スパッと切り込んだデザインに完成させています。説明しなくても伝わるハッピーとエコが、グランプリにふさわしい作品だと思いました。
佐藤 可士和
エコロジーについて概念的に捉えると、途端にリアリティーがなくなりがちですが、「ガリボール」のようなシンプルさによって示すことが大切だと思いました。審査員の間でも、「アタリ」以外のアイデアが次々出てきたことからも、広がりを感じるとともに、モノを超えてコミュニケーションがデザインされていると思いました。
鈴木 康広
「アタリ」のアの文字が見え始めてからさらに使い続ける時間の流れに、文房具と人との関係性を見出せる作品です。商品としては事前の告知無しにひっそりと販売し、人々の間で噂が広がるような仕掛けがあってもよいと思いました。
田川 欣哉
優秀賞

MIZUHIKIBAND(ミズヒキバンド)
作者
麻生 遊
作者コメント
水引の蝶結びは、簡単に結べる事から 「何度あっても良い」という意味で 祝事全般に使われています。 輪ゴムは「簡単に結べる紐」だとも言えます。 蝶結びが付いた輪ゴムは、 何度でも使える贈り物の最小限のパッケージとなります。
見た目がチャーミング。受け取る側が嬉しい気持ちになる魅力的なアイデアです。パーソナルギフトは、さらに広がる可能性があるので期待できるものです。水引をゴム製にした、似た形のものが世の中に既にある点が残念でした。
川島 蓉子
ギフトというよりも、一般の店舗で梱包用として使うような業務用にしたい、という発想が良いと思います。ユーザーに対していろいろなことを強要しない、カジュアルな存在を目指している点が評価できます。ただ、もう少し魅力的なパッケージを考えてほしかった。
佐藤 可士和
輪ゴムという気軽さに対して、それを繰り返し使うことへの着眼に惹かれました。捨ててしまいがちなものも小さな工夫で捨てない瞬間があります。その瞬間の「気持ち」の結び目のように見えました。水引にもリボンにも見えるところが、かしこまらず、用途に広がりを見せるのではないかと思います。
鈴木 康広
この輪ゴムをもらった人が、次に別の人にあげる。つまりリユースを通して気持ちが伝搬されるということに好感を持ちました。着想の原点と着地のレベルが高い作品です。
田川 欣哉

Stoop(ストゥープ)
作者
ユカ ヒヨシ
作者コメント
芝生に座りたいけど、お尻は汚したくない。 石のベンチは、固くて冷たい。 座りたいところに、イスはない。 屋内外で使える樹脂製の座布団があれば、 個人の創造性や行動範囲の柔軟性を サポートできると思いました。 年齢や場所にとらわれず、 人の集い方、遊び方、そして働き方をもっと自由に。
1枚にまとめられたプレゼンボードを見ただけで、使い方や使う環境が伝わってきました。実際のプロダクトとしての座り心地が重要なポイントなので、これからがんばってほしいです。
川島 蓉子
「ストゥープ」は、NYの高層ビルによくあるエントランス前の階段そのものから名づけたということ。そこに座ってリラックスするアイデアだというデザインの背景が、ネーミングからもう少し伝わると良いと思いました。
佐藤 可士和
普段、NYで暮らしている方から見ると日本の座布団が親切なものに見えたという何げないコメントに、静かな驚きを感じました。どこで使うための道具なのか、個人のものなのか施設の一部なのか、線引きがあいまいなところにこの作品のポテンシャルを感じます。フリスビーのような座り心地を想定しているということから、遊び道具を兼ねる可能性もあるのではないでしょうか。
鈴木 康広
芝生や砂場など屋外の共有スペースをもつ施設では、リーズナブルなコストで無理なく展開できそうな期待感が持てました。
田川 欣哉

タックメモ スタンプ
作者
福嶋 賢二
作者コメント
いらなくなった新聞や雑誌、 お気に入りの紙をポン! 押すだけで誰でも簡単に 付箋が作れるエコロジーで楽しいスタンプ。
確実にニーズがありそうだし、楽しいアイデアだと感じました。ただし、コンペの応募作品として考えるならば、コクヨありきの商品デザインではなく、ユーザーありきで発想してほしかったと思います。
川島 蓉子
最終プレゼンテーションがまるで商談のようでした。商品化を前提に、と主張する姿勢はとても評価できます。とはいえ、コンペの主旨に合わない部分も多く、コクヨに媚びている印象が強すぎました。
佐藤 可士和
第一印象として、実現できれば使ってみたくなる商品だと思い、わくわくしました。一見、コクヨに媚びすぎたプレゼンテーションに見えましたが、できた状態をイメージさせる重要性は感じます。実現できてこそ意味のある提案なので、握り心地だけでなく、機構面も含めてプロトタイプを提示するべきだと思いました。
鈴木 康広
切り抜かれた紙が付箋になるアイデアは冴えていました。製品のデザインに独自のアプローチがあれば、なお良かったと思います。
田川 欣哉
特別賞

shapes
作者
礒野 楓
作者コメント
何かを覚えようとする時、情報の種類はいくつかある方が覚えやすい。言葉と色や形といったイメージを一緒に頭の中に取り込めば、ラクに楽しく暗記ができます。イメージは言葉から連想するも良し、カードの中から見つけ出すも良し。
新しいカードに書くたびに自分の言葉のコレクションを増やしていくような感覚で楽しく覚えられるでしょう。
チャーミングな感じが詰まっているユニークなアイデアだと思いました。単語カードという既製品に対するアイデアに留まらず、次のステップでは、世の中にまだ存在しないものを発想してみるのも面白いと思います。
単語や年号を覚えるのが苦手なので、実際の効果はわからないが、こういう形があったらいいですね。 本当に使って覚えられるか定かではないが、着想がいい。 審査会では、机に並べて神経衰弱のように使うアイデアだと面白かったかも、という意見が出ました。
厳密な回答を求められる単語の意味よりも、イメージや発想にまつわる記憶を高める方が良かったかもしれません。現状ではそういった用途が日常的に一般化されていないことが残念です。自分でカードそのものを作ることに魅力を感じたので、商品というよりも方法のデザインとして評価しました。
鈴木 康広
単語カードの「めくりながら覚える」というスタイル自体を変えてみることにまで発想を伸ばせれば、なお良かったと思います。
田川 欣哉

Blindsense Note
作者
北川 梓
作者コメント
四角形の並ぶページ
半透明のページ
ふわふわなページ
Blindsense Noteは、全てのページが異なります。
さまざまなページから得た気付きや発見に合わせて好きな所から使い始める。
明確な使い始めや使い終わりはなく、いつまでも持ち歩いけるノートです。
創造的で夢がある素敵なデザインです。ただ、使い手としては、差し出されるだけだと使い方が良く分からない。説明なしで伝わると、もっと良かったと思います。
説明がないとどういうものなのか分からず、難しい。 アイデアをじっくり聞けば分かるが、アナウンスなしだと、書きづらいページが不良品だと思われてしまうかもしれない。分かりやすさは重要なポイント。
普段、僕自身も自己流の方法でノートを使っているので、無意識の領域を引き出すという発想に深く共感します。このノートは主にクリエイティブな活動をしている人のためのものだと思います。より多くの人にその機能を伝え、活用してもらうためにはどうしたらよいか、ぜひ、引き続き探求して頂きたいです。
鈴木 康広
好きな作品ですが、実現したいコンセプトが少し複雑すぎたかもしれません。もう一歩、アイデアを純化させられれば、もっと良かったと思います。
田川 欣哉

NON-NEWSPAPER
作者
SEISHUN FILM 福田 雄介
作者コメント
読み終えられた「新聞紙」はその素材特性と手軽さがあいまって、古くから暮らしの知恵と共にさまざまな場面で活用されてきました。
しかし今日の情報化社会において新聞というメディアのあり方は縮小しつつあり、その便利でエコな「紙」は家庭から姿を消すことが多くなっています。
そこで情報を伝えるための「新聞紙」としてではなく、生活に彩りをあたえ人々の心を豊かにする「新聞紙」のあり方を考えました。
目のつけどころがユニークで素敵だと思いました。提案された商品の色柄や、使い方の提示方法は、リアルで的確だっと思います。ただ類似品があったこと残念でした。
着想がすごく良いと思ったが、ピンク色の新聞紙が実際に世の中で販売されているのがわかったので特別賞となりました。 グラフィックセンスやダミーの作り方は非常に完成度が高い。 りんごに見えたり、柿が箱に詰められているようにみえたりするアイデアは良かったです。
新聞という身近な素材ということもあり、さまざまなイメージが広がりました。結果的に類似品が見つかり残念でしたが、プレゼンテーションの時に追加で提案されていた、包むことで果物のように見せるアイデアも秀逸だったので、個人的には商品化を期待しています。
鈴木 康広
本当の新聞のように、この紙が毎日、発刊されてコンビニなどの新聞ラックに並んで売られていたら面白い風景だろうなと思いました。
田川 欣哉

Pencil Journey(ペンシルジャーニー)
作者
平田 昌大
作者コメント
「Pencil Journey」は、たった1本で25,000km分の世界旅行ができる鉛筆です。
目指す場所に到達した時の感動。
途中で行った知らない国々。
底がすり減ったぼろぼろの靴。
そのすべてが旅の持つ価値です。
たった1本の鉛筆もそんな気持ちがあれば、
愛着をもって最後まで使うことができるかもしれません。
夢を感じるストーリーがある。自分の居場所を基点に、世界に想像が広がっていくような考え方に魅力を感じました。そこをもっと膨らませるアイデアにして欲しいと思います。
「書く」ことと「旅」との連想にイメージが広がり好感を持ちました。プレゼンテーションを受けて、鉛筆の芯の太さや長さを具体的な距離に換算することに当初のイメージとのギャップを感じてしまいました。一般化せずにイベントなど具体的なテーマとともに使う鉛筆として展開してもよいのではないかと思いました。
旅のイメージの表現として、国旗と数字の表示が少し弱いのではと思いました。もう少し詩的な部分があっても良かったかもしれません。
田川 欣哉
審査員総評(※審査員の肩書は審査当時のものを掲載しております)
川島 蓉子(伊藤忠ファッションシステム株式会社)
人が日々暮らしていく中で、さまざまなモノやコトに触れる時、何らかのかたちで、デザインというフィルターを通していると思います。その意味では、人とモノやコトをつなぐ存在としてのデザインの果たす役割はとても大きなもの。魅力や期待を詰め込むことで、人は未来や希望を感じるのではないでしょうか?今日から明日に向けて、既に未来は始まっている。その入り口の部分を作る要素として、デザインの果たす役割は、ますます大切になってきていると思うのです。今回のアワードでは、たくさん素敵なアイデアが集まりましたが、ハッピーに向けてもっと大きな飛躍があったら、もっと良かった。そんな風に感じました。
佐藤 可士和(サムライ代表)
「Happy」そして「Ecology」。現代社会において絶対的正義のテーマに正面から向き合わなくてはならない今年の課題は、非常に難しかったと思う。このような本質的な問題を解決していくことこそが、本来デザインに期待されている役割なのだということを、審査を通して改めて深く考えさせられた。「Happy」といっても、いろいろなレベルでの「Happy」がある。「Ecology」といっても、抜本的な解決方法など容易くは見つからない。我々デザイナーは本当にそこに対して素晴らしい答えを提示でるのか?いや、決してあきらめてはいけないのだ。何故なら、おそらくクリエイティブにしか、そこをブレイクスルーすることができないのだから。 。
鈴木 康広
「HAPPY×DESIGN」というテーマは、デザインの視点から「よろこび」を捉え直し、人間の道具づくりの原点と未来をつなぐ、新たなスタートラインを示しているように思いました。グランプリの《ガリボール》は、誰しもが経験的にわかる「アタリ」のうれしさと、「使い切る」達成感をかさね合せた秀逸な提案でした。シンプルなアイデアの中に、持続的にモノと付き合う感覚や、パーソナルな視点を大切にしたコミュニケーションのヒントが濃縮されているように感じました。日常の些細な出来事の中に温存されている「よろこび」の種を発見し、水を与え、新しい体験として鮮やかに昇華させるデザインの力を再確認することができました。コクヨデザインアワードという「対話」を通して見えてくる、身近な道具がひらくコミュニケーションの可能性にこれからも目が離せません。
田川 欣哉(takram design engineering代表)
今年はHAPPY&ECOLOGYとHAPPY&PUBLICというテーマでした。それぞれの言葉はあまりに当たり前に広く使われている言葉であるがゆえ、応募者のみなさんは作品のコンセプトにシャープなフォーカスを与えることが難しかったのではないかと思います。その中でグランプリと優秀賞に選ばれた作品は、最小のデザインながら、人々の行為やコミュニケーションを引き出すことができるものが揃いました。モノを媒介として人と人が繋がる、それが今回のテーマの奥に垣間見えた気がしています。
黒田 章裕 (コクヨ株式会社代表取締役社長執行役員)
11回目の開催となりました今年のコクヨデザインアワードは「HAPPY×DESIGN」をテーマに、使う人が幸せになるデザインや、コミュニケーションを活発にすることで豊かな未来を創造するデザインについて、改めて考える場となりました。また、部門別にサブテーマを設け、ステーショナリー部門では「HAPPY×ECOLOGY」、ファニチャー部門では「HAPPY×PUBLIC」としました。エコロジーとパブリック、という幅広い課題に迷われた応募者の皆様も多くいらっしゃったことでしょう。しかし、国内外から1217点もの作品が集まりましたのは、国際的アワードへ成長した証でもあります。ご応募いただいたすべての方に感謝を申し上げるとともに、今後とも積極的に生活のデザインを意識し、魅力ある日本のデザインを発信していきたいと思っております。
表彰式の様子
「HAPPY×DESIGN」のテーマに似合った、楽しい作品が揃った今年のデザインアワード

「HAPPY×DESIGN」をメインテーマに、ステーショナリー部門「HAPPY×ECOLOGY」ファニチャー部門「HAPPY×PUBLIC」の2部門制でデザインを募集した「コクヨデザインアワード2013」。世界各国から計1,217点の作品が集まり、そのなかから1次審査を通過した13点を対象に最終審査が行われました。そしてグランプリ(1作品)と優秀賞(3作品)、特別賞(4作品)が決定しました。
最終審査はコクヨ品川オフィスで開催されました。ノミネートされた方々がパネルや模型を使ってプレゼンテーション。審査員にそれぞれの作品を積極的にアピールしました。
その後、審査員だけで討議をして、数時間後には審査結果の発表が行われました。
発表は満員となったコクヨホールで。多くの人が注目するなか、コクヨの黒田社長からグランプリとして名前を呼ばれたのは玄 多仁(ヒョンダイン)さん。作品「ガリボール」が栄冠に輝きました。使い切ると当たりがでてくる、当たりクジ付きボールペン。さらに、当たりがでたらもう1本プレゼントというユニークな作品。シンプル、わかりやすい、楽しいなど、各審査員から高い評価を得ました。その後、優秀賞と特別賞の発表があり表彰式は終了。壇上にはたくさんの笑顔が並びました。
表彰式の後は審査委員によるトークショーが行われました。グランプリをはじめとする受賞作品ひとつひとつに対して審査員が講評。自体が来年の作品づくりに向けてのアドバイスやヒントにもなる貴重な話を聞くことができました。夜からは懇親会。審査委員と受賞者の間でクリエイティブな話題が交わされ、充実した時間をみなさん楽しんでいらっしゃいました。